会長対談
災害と国土を語る

2011年3月11日に発生した東日本大震災から12年が経ちました。今回の会長対談は、陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園や陸前高田市立博物館など東日本大震災における陸前高田市の復興プロジェクトに携わった建築家・多摩美術大学学長の内藤廣さんをゲストにお迎えし、復興や防災・減災への考え方、また大災害にも強い国土や地域のあり方を語ります。
東日本大震災の復興
羽藤 寺田寅彦さんの「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉にもあるように、災害の復興後は記憶との闘いであることが指摘されます。今なお続く福島復興に関心を向ける人も少なくなりました。内藤先生は特に陸前高田市の復興にご尽力され、現在も被災地との関わりを続けておられます。おそらく建築家の立場を超えてまで関わった部分もあると思いますが、これまでの12年間でどんなことを思われますか。
内藤 津波で被災した陸前高田市立博物館が昨年11月に再開館して、この間改めて訪れたんですけど、明治三陸地震津波(1896年)の展示を観て、「過去の震災からの教訓」について認識を新たにしました。
明治三陸地震は震度 2から3ぐらいの長い揺れだったそうです。それほど危機を感じるような揺れではないのですが、30分後、広田村では26.7mと、東日本大震災の倍ぐらいの高さの津波が来たそうです。事前復興を考える際に、東日本大震災の経験をそのまま教訓にして、震度や津波の高さ、時間を想定して避難マニュアルを作成すると間違うかもしれない。三陸の復興は決して成功事例として考えない方がいいと私は思っています。自然が何をするのか、本当のところはわからないのです。残念だけれど人間はこの先も失敗を重ねながら災害に向き合っていくのだろう──というのがこの12年の率直な思いです。
羽藤 高田松原津波復興祈念公園には、各地からいろいろな世代の方が訪れ、東日本大震災津波伝承館で展示を見た後に、献花の場、追悼の広場を通って海を望む場へ歩いていく。災害とは一体どういうものかということを、自分が暮らす地域に持ち帰って考えるでしょう。防災や復興に対して、そうした動機付けとなる場所、気持が奮い立ってくる場所が被災地でもあり、次の災害に向けた学びの場が三陸の地にできたことは素晴らしいと思います。
内藤 ありがとうございます。あれはたくさんの関係者が立場を超えて協力しあった成果です。当初、私は東北地方整備局の追悼祈念公園の委員でした。祈念公園をどういう姿にするのかという会議の議論が堂々巡りでつまらないので、委員会レポートの表紙にスケッチを描いていました。それを委員のみなさんに見せたら、それがいい、という話になりました。それで委員長の中井検裕さんに「それなら私は委員を降りて、手を動かす側に回る」と話して、いくつかの経緯を経て設計者として携わることになったんです。
羽藤 土木の仕事はスケールが大きいので、幾つかの組織で議論しながら構想が固まっていって最後に図面が描かれますけど、内藤先生は自らの足で現地に入り、自らの手を動かして考えるところから関わっていったのですね。そのようにして考えようとする建築家は必ずしも多くはないと思いますが、内藤先生の場合は自身の流儀なのか、委員会方式に対しての問題意識からだったのでしょうか。
内藤 問題意識からでしょうね。委員会では、やはり型通りのことしかできません。追悼や祈念の施設をつくることはやはり精神の問題だと思うんですよ。被災後に陸前高田の波打ち際に立って見た海は凪いでいて、その逆側の陸にはほとんど何もなくて、陸地と海とがほぼフラットな状態でした。その光景を目にして、「自然は社会や人間にいろいろなことを仕掛けてくるけれど、こうまでしなくてもいいだろう」という思いが口からこぼれ出ました。あの感情ができるだけ色褪せないように、皆が集まってきて思い出せる場所をどうやってつくるか。私が考えたのはそのことだけです。
防潮堤の委員会では羽藤さんともご一緒していましたが、防潮堤は地域にとって防災上、必要だけれど決して完璧ではないし、海を感じられないという声もある。ある意味では、人間社会の自己矛盾みたいなものがそこに象徴的に表れています。だけど広田湾は美しい姿でそこにあるんです。あんなにきれいな海が、ある瞬間には人間にとって脅威になる。その幅みたいなものを少しでも感じてもらえるといいかなと、「海を望む場」として防潮堤の上に献花の場所をつくりました。通常は防潮堤の上にあんな場所をつくるなんてあり得ないのですが、ここはかなり無理を言いました。全ての施設は、あの小さな場所を成り立たせるための背景にすぎません。
伝承館や道の駅を訪れた人は、ほとんど全員が防潮堤の上まで行きます。海を見て、海を感じて帰ってもらう。そこはうまくいったのではないかと思っています。
羽藤 過酷な自然がもたらした凄惨な光景を見て、ここまでやるのかという感覚、それでもやっぱり広田湾は美しいというのはとてもよく分かります。被災後に地域の子どもたちが描いてくれる絵が、直後はとても暗い絵ばかりだったのが、復興が進むにつれて少しずつ明るくなり、広田湾を描いた絵も増えてきました。復興に携わる人たちが諦めないで現地に通い続けて実現できたこと、また住民の方々が辛い経験をしながらも「この土地でもう1回生きてみよう」という前を向く思いが呼応したのではないでしょうか。内藤先生を中心に素晴らしいエンジニアたちの力で思いが鼓舞されたことを強く感じています。

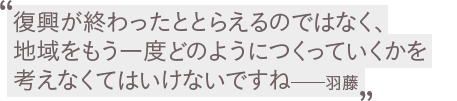
復興は国土をどのように変えたか
羽藤 東日本大震災の前と後で、社会はとても変わったと思います。三陸全体、あるいは東京との関係も含めて、復興が国土をどのように変えたか、考えをお聞かせください。
内藤 まず、三陸の人たちは強いと感じました。岩手県の野田村にも通っていたんですが、ある時、小田村長が空を見上げて「俺たちはこうやって生きてきたんだよなー」とつぶやいたんですよ。「こうやって」とは、この地域の人々は1000年ぐらいの長い間、津波に襲われながら、反省しながら、生き延びて、現在に至っている。防潮堤もそうですが、復興は国や行政が主導しているもので、地元の人たちはもちろんそのことに感謝する一方で、自然を甘く見ない冷静さも持ち合わせているなと思うことがよくあります。
復興については、もっと違ったやり方があったかもしれないなどと今になって言われていますが、当時はあれが精一杯だった。次は何とかしたいと思うんだけど、財政のこともあり二度とあんなふうにはいかないように思います。
羽藤 12年超の時間が経ち、初期の復興や今も続く福島の復興について、様々な反省や結果が出てきています。復興が終わったととらえるのではなく、地域をもう一度どのようにつくっていくかを考えなくてはいけない。復興道路として整備されていた三陸沿岸道路(仙台~八戸)359 kmが2021年に全通しましたが、これをどう使いこなしていくか。高台移転した地域では住民の高齢化が進んでいて、大都市近郊にかつてつくられたニュータウンと同様の問題が起きている。解かなければいけない問題は新たに現場で生じています。三陸沿岸で考えることは、日本海沿岸の地域問題だったり南海トラフ地震などの防災・減災に活きてくるので、常に現場を考え続けなくてはいけないですね。
内藤 日本の戦後から約80年が丸ごと問われているように思います。大きな災禍の時にこそ国家というものが機能するわけです。でも、戦災復興の時からやるべき問題を本当に解決してきたのか。東日本大震災でこれだけ大きな被害があり、多くの問題が浮上して、道路を含めたインフラ整備、地方自治の問題、人間の権利の問題、コミュニティの問題、原発の問題など、全体をもう一回検証し直す契機となったはずなんですが、現実にはあまりそうならなかったことが気になります。
羽藤 「全国総合開発計画」で戦後やってきたのが、2000年に行財政改革が実施されて、2001年の中央省庁再編で国土庁は運輸省、建設省、北海道開発庁と統合して、国土交通省が発足し、内閣府の機能強化で国土庁の防災行政業務や経済企画庁の業務も内閣府に承継されるかたちで、国家の運営体制は大規模な改革が行われました。そのようにしてつくられた国家をどのように機能させていくか。東日本大震災やコロナ禍では正面から問われた。補償すべきは個人か世帯なのか、復興に際して地域を復原するのか、それとも人間に対して支援するのか。もともと次の世代に向けた制度設計もできていない中での東日本大震災の復興があり、またコロナ禍での被害は復興過程にあった三陸をはじめ日本全体を覆っていったというのが、ここ数年起こったことだと思います。
内藤 コロナ禍で議論になった人間の権利の問題や行動制約については、羽藤さんが東日本大震災の時に話をされていました。災害時には政治的な空白や民意の空白状態が生じるので、ある意味ではいろいろなことがやりやすくなるとは思うのですが、本来、そうした議論は非常時ではなく、平和で皆が冷静な時に深めておくべき話だと思うんです。
羽藤 その議論は緊急性を帯びています。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、あるいはChatGPTなどの生成AIがジェネレーティブに様々なものを目の前に差し出すことをどう受けとめるのかも含めて世界規模で変化が加速していく中で、個人や社会、国家や都市がそれに対応できるかどうかで峻別されるような時代観があります。そんな中、国土の現場で問われるのは構想力や実行力で、今までにないリスクを自身が取っていかないと、普通にやっているだけでは落ちていってしまうと認識せざるを得ない。
陸前高田の復興過程での内藤先生の試みは、通常の仕事の流れでは生まれなかったところを、自身で現場を歩き、実際に手を動かしていくことで流れを変えることができたのだと思います。個人個人がそういう思いきったことをしていかないと、これからは都市、国土、地域、社会、個人、家族も生き延びられない。それぐらい大きな変化が訪れていることを痛感しています。
内藤 私は今年度、多摩美術大学の学長に就任して、執行部とか先生方とかなり真剣にChatGPTに関しての話をしています。今の生成AIは文章を中心に語られていますが、実は形の話でもあって、デザインやアートにとっても大問題なんですよ。美とは何か、オリジナリティとは何か、生命とは何か、その本質が問われるようになる。今までの社会的なしきたりや慣習的にやっているものが全部打ち砕かれていくことは、新しい社会にとっても面白いし、前向きに考えたいと私は思っているんです。
ChatGPTが今より進化している前提ですが、大きな災害を想定すると、数万人単位の住民が集まって、「どんなまちにしたいか」「どんな暮らしがしたいか」を話してもらうことも可能でしょう。そこでChatGPTを使うとしたらどういうことが可能なのだろう、などと考えます。「逃げ道はこんなだったらいいよね」「裏の路地があったほうがいいよね」「お年寄りがいたらこうだよね」とか語り合って、それを即座に形にして見ながら、「いや、ちょっと違うかもしれない」「こうしたらどうだろう」などと、制度設計やお金の問題も含めて画像を見ながら皆で議論する。そういう民意のあり方で地域をつくることが可能かもしれない。先の震災でみんなが一番苦労したのが合意形成ですからね。その道具として使えるのではないかと思います。
羽藤 合意形成は東日本大震災の復興過程でもやはり大変でしたし、都市部の再開発など通常の公共事業でも困難です。生成AIもいろいろな意見の集合体に対する形のバリエーションも出せる技術はできています。次の復興にどう備えるかという時に、合意形成の仕方そのものに僕たち自身が声を挙げなければいけないところはありますけれども、どういうふうにそれを形づくるかに関して生成AIが介在できる余地はかなりあるのではないでしょうか。

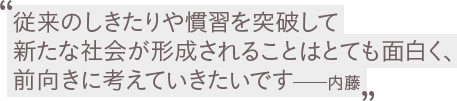
これからの国土像におけるアートへの期待
羽藤 内藤先生ご自身が建築家であることは変わりませんが、東京大学の社会基盤の教授を務められ、今度は多摩美術大学の学長に就任されました。美術がまちづくりや国土計画、都市計画あるいは建築に対して果たす役割はとても大きいと思うんです。首都直下地震や南海トラフ地震を見据えて、未来の国土像・国土構造に対してアートが果たす部分にどのような期待をされていますか。
内藤 若い世代の人たち、なかなかいいですよ。ここ数年でバーチャルな世界がいっきに広がったわけですね。でも、エンジニアリングとして広がってたくさんの技術者も生まれているんだけど、どのようにその世界をイメージし描けるかはアートやデザインをやってる人間にしかできないわけです。だから面白い。今は、油絵や日本画や版画を学んだ学生たちの多くが上場企業に就職していきます。それだけ求められる人材になっているのです。「近未来に対するセンサー」という彼らの特殊能力をフルに活用しながら広がった世界をどう描いていくか。それが東京大学とは違うところかな。一方でクリエーティブな部分でも、ChatGPTなどでよく問われるオリジナリティとは何かとか、最前線を見ている感じがします。こうした機会を得て、私はこれまで以上に青臭い話を、正面からしようと思っています。
要は広い意味での「文化」なんですよ。戦災復興の時にも基本は文化が支えになった。ある人のエッセーで、戦災で日本の都市が焼失して社会が絶望感に満ちている時に、辺鄙な片田舎の村でおばあさんが美しい日本語を話すのを聞いて、「この国は大丈夫だ」と思った、というエピソードを読んだことがあります。われわれは日本語のレトリックの中でいろいろな話をしたり考えたりしているわけだから。つまり、文化はある1つの文明が蘇生するための復元バネなんです。危機に直面した時に、本当に盾になるのは文化なのではないか。文化まで奪われてしまうと、何も残らない。
朝日新聞の記者だった本田優さんから聞いた話ですが、中曽根康弘さんに「国というのは何ですか」と聞いた時に、「文化を守るための装置かな」と答えたそうです。私はこれが核心だと思っています。文化って社会の外にふわふわとまとわり付いているようなものだと思われがちだけど、実は逆で、社会制度や国家戦略や法律といった仕組みというのが、文化を守るための装置なのだというのは、最近聞いた言葉の中では一番衝撃を受けましたね。その通りだと思います。
羽藤 僕たちが何か大きなものをつくるとか災害復興の局面では、壮大な物語だったり、図と地なら図の方を、経済と文化なら経済を重視しがちです。でも、それだけではなくて、人間にはもっと低層に流れているヘテロトピアとでもいえばいいでしょうか、日常につながる異なる物語がある。アートや文化はそこに眼を向けて無視されがちな異世界を増幅させ、表現し、再生のバネにしていくことができる。そうした素養や才を受け入れる余力が、国土にどれだけ残っているか、育っているか、それこそが大事だと考えるコモンセンスが私たちの中にあるかどうかがこれからの地域像、国土像にとっては極めて重要です。そういうのを大切にしている地域は生き残れるし、そうではない地域は漫然と消滅へ向かっていくかもしれない。
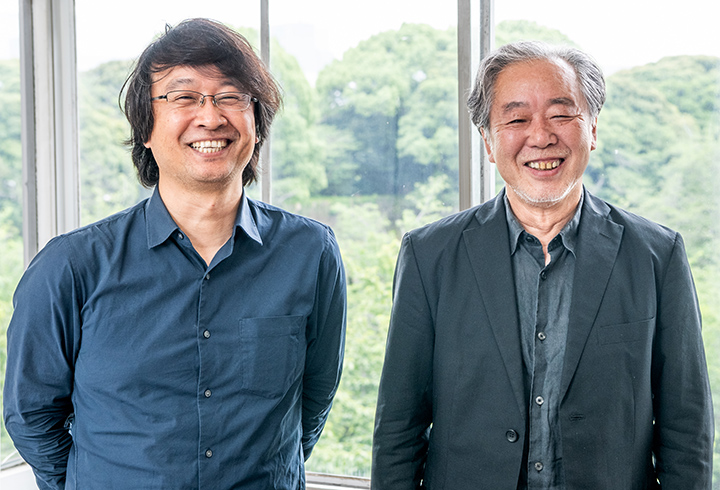
大災害にも強い国土像・地域像とは
羽藤 関東大震災後の帝都復興によって東京を含めて国土全体も大きく変わりました。首都直下地震、南海トラフ地震など予測される大災害に向けてどういう国土像や地域像を描いていくべきだとお考えでしょうか。
内藤 私は大都市以外の日本の国土がどれくらい豊かであるかに関心があります。日本の都市人口比率は約8割ですけれど、実は都市以外が健全でないとそれが成り立たない。私は渋谷駅周辺の再開発にも学識の立場で携わっているけれど、その周りに広がっている渋谷という街独特の匂いというかあのアノニマスなエリアが渋谷という街を成り立たせていると思っています。この「超高層ビルと渋谷の街」という図式は、そのまま「東京と東京以外」「都市と地方」とリンクしていて、東京以外、地方が元気になる方策を真剣に考えないといけないと思っています。
全くの専門外ですが、食糧自給率を上げることもその1つだと考えています。この間、イタリアで暮らしていた人と話したら、イタリアの地方の人たちの暮らしは大抵のことではほとんど揺らがない。GDPがどうであれ、政権がどうであれ、世界がどうであれ、基本的に飢えることがない。だから強いんです。日本はどうでしょうか。東京以外、地方がそれぐらいの存在感と自信を持つ状態になればいいと思うんですが。
羽藤 農業やエネルギーは安全保障上、非常に重要な問題です。日本の一番の弱点ですけれど、例えば、地方部には近世由来の豊かな用水網や小規模な水力発電がある農村では、良質のお米が収穫できて、それを活用しておいしいお酒がつくれるといった文化が継承されてきました。
戦災復興の時代に都市部では生活が大変だった中で、地方に疎開して受け容れてきた時代があった。日本の地方都市あるいは地域社会の美しさや豊かなポテンシャルをどのように磨いていけるのか、若い人たちはとても関心を持っている。リニア、自動運転、ドローンの導入を通じて新たな倫理と社会的受容を地域が獲得するために私たちは全力を尽くさなければいけない。それによって新たな集積を生み出しつながっていけば、これからは地方の時代になると思います。
これまでは集積の経済で、東京あるいは都市部のターミナル経済が強かった。でもその外部不経済を考えると、コロナ禍を経験して以降は働き方を含めてこれまでとは異なるライフスタイルが注目されています。これからの地域像として、災害や安全保障に強い部分を磨いていくということですね。
内藤 コミュニティ自体が崩壊している中で、農村の風景だけ残すみたいな話は本末転倒です。里山があり、農地があり、古い集落があるという風景は、何百年もかかって先祖がつくってきた「生存の様式」なんです。だから、昔に戻すという感覚ではなくて、羽藤さんが言われる通り、これからの国土をつくっていく上で極めて合理的な「生存の様式」が生まれてくるという国土像を描く方がリアルで面白いですね。要するに生きるための風景だからね。その方が説得力がある。
羽藤 東京は人もたくさんいるので多様な文化に触れることができる一方で、満員電車に揺られて通勤して子どもは塾に通うというような組織文化です。それに対して地方がどういうオルタナティブをこれからつくっていけるかが重要です。地域では今、若い人も年配の人もチャレンジしています。一般的な東京の価値観ではリスクのある行動に見えても、挑戦が連鎖していく中で新しい文化が生まれ、それが次の災害に対しての備えにもつながっていくのではないかと感じました。今日はどうもありがとうございました。
(対談実施:2023年6月23日 撮影:大村拓也)

