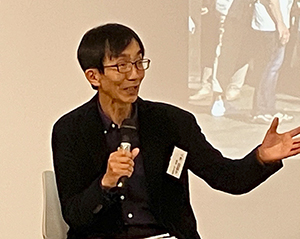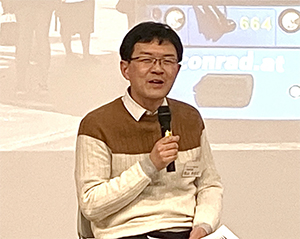地域公共交通総合研究所シンポジウム 「持続可能な交通まちづくり─欧州の実践に学ぶ」 報告
2025年1月8日、当会が後援する新春フォーラム2025((一財)地域公共交通総合研究所 主催)が岡山にてハイブリッドセミナー方式にて開催されました。開会の挨拶として小嶋光信氏((一財)地域公共交通総合研究所 代表理事)より、「持続可能な交通まちづくり―欧州の実践に学ぶ」(宇都宮浄人氏/柴山多佳児氏 著)のご紹介を頂きまして、日本では赤字の公共交通をどうするか等の議論が主ですが、ヨーロッパでは本質的にQOL(Quality Of Life)を高める交通、ウォーカブルなまちづくりのための交通のあり方を考える観点が主である、本書はその点について実践例と共に詳細に書かれているとのことです。
そして、今回著者お二人と有識者を含めて、欧州の実践から何を学ぶべきかの議論が交わされました。
宇都宮浄人氏(関西大学教授)より、オーストリアの地方都市グラーツでは、現在のモビィリティ戦略として、「持続可能な都市モビリティ計画」(SUMP:Sustainable Urban Mobility Plan)の策定がしっかりと進められている、SUMPは「人のための計画」をモットーに、都市のアクセシビリティと生活の質を向上させることを目指すものであり、市民が参加し一体となって関与して進められることが重要視されているとご説明を頂きました。
柴山多佳児氏(ウィーン工科大学上席研究員)はスペインの地方都市ポンテペドラについて、人口約8万人の内6万人が6km2の中心部に住んでいる都市であり、「歩いて住みよいまち」を徹底的に研究し、歩行者優先の街路づくりに転換していることのご紹介を頂きました。
床尾あかね氏(岡山大学准教授)はフランスの都市ナントについて、「都市圏交通計画」(PDU:Plan de Déplacement Urbain)に基づいて整備が進められ、自動車に強い制限を設けて歩行者等と共存できる交通計画を推進しているとご説明を頂きました。
大上真司氏((一財)地域公共交通総合研究所副理事長)は北欧を訪問して、「誰もが参加出来る活力ある豊かな社会へ」を実現することへの市民の本気度が日本よりも強いという実感を持たれたというお話がありました。
藻谷浩介氏((株)日本総合研究所主席研究員)より欧米(海外)と日本の道路に対する基本的な考え方の違いについて、日本人は道路整備に多くの税金が費やされているにもかかわらず、道路を無料の施設と考える傾向があり、それが自動車の交通分担率が高いことの要因の1つであるというお話がありました。
コメンテーターとして、家田仁氏(政策研究大学院大学特別教授)より、地域の交通まちづくりの問題解決は、地域公共交通が「政治的イシュー」として位置づけられるかどうかに依るところが大きいというご示唆を頂きました。
本フォーラムを通じて、日本の持続可能な交通まちづくりの実現のために、我々が望む都市交通の形を行政、政治に訴え続けることの重要性を強く感じました。
大成建設(株) 新田直司(広報委員)